期間の『ズレ』は悩みのタネ ~子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の取扱いを整理
温室効果ガス排出量の算定期間
サステナビリティ開示基準は2025年3月に確定しましたが、その過程では「指標の報告のための算定期間に関する再提案」という公開草案の公表を経ています。
当初の公開草案では、温室効果ガス排出量の開示に関し、「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づき当局に報告済みの直近データを利用する方法も許容することが提案されていました。
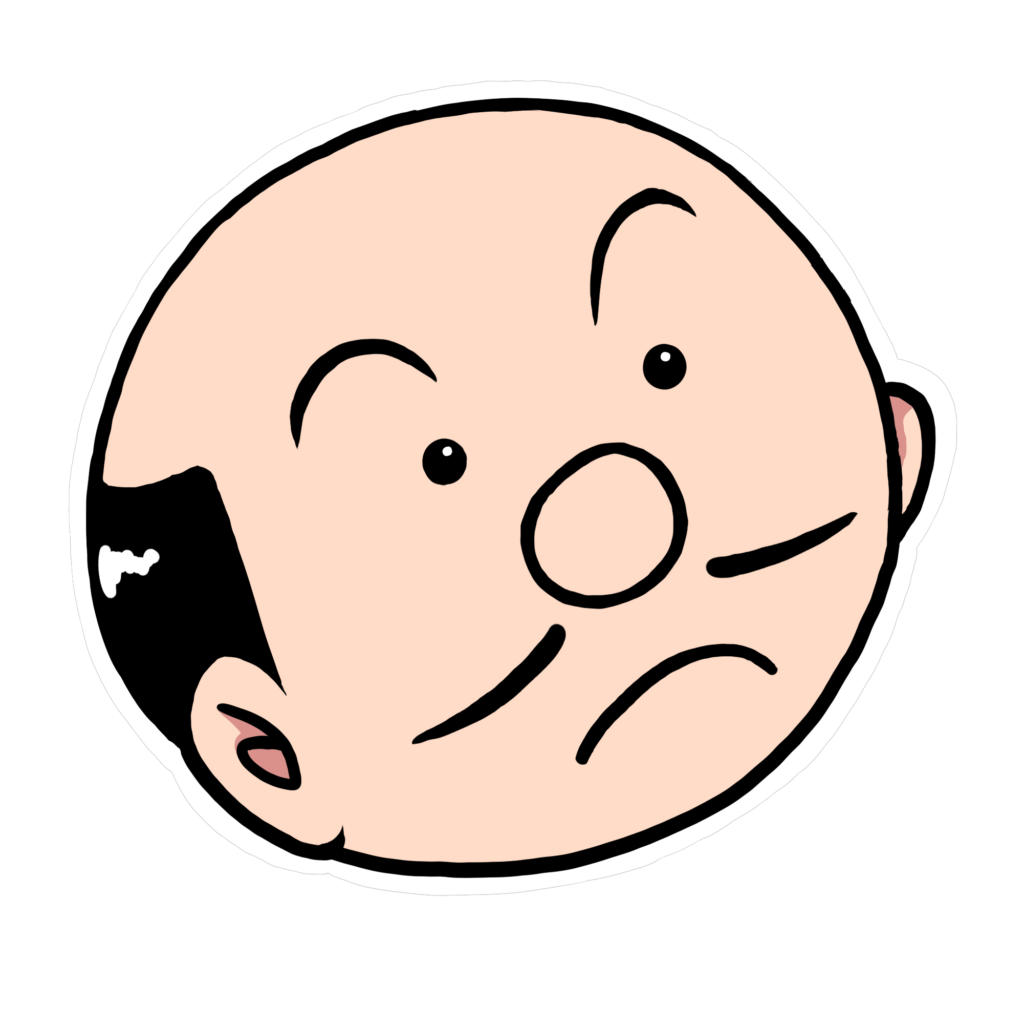
当初の公開草案では、実務上の負担軽減を重視していたんだね。
しかし、温対法に基づく温室効果ガス排出量の報告期限は毎年7月末(※特定事業所排出者の場合)であり、また、温室効果ガスの種類によって暦年ベースないし年度ベースといった異なる算定期間が定められています。
そのため、3月決算企業がサステナビリティ関連財務開示において温対法に基づく直近データを用いると、温室効果ガス排出量の算定期間とサステナビリティ関連財務開示の報告期間(すなわち会計期間)に大きなズレが生じてしまいます。
この「算定期間と報告期間のズレ」によって情報の有用性が低下するとの意見が多く寄せられたため、基準は再提案を経て、最終的に算定期間を報告期間に合わせる(合理的な方法で期間調整する)ことを求める内容で確定しました。
子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の取扱い
期間の『ズレ』は、さまざまな場面で悩みのタネになります。
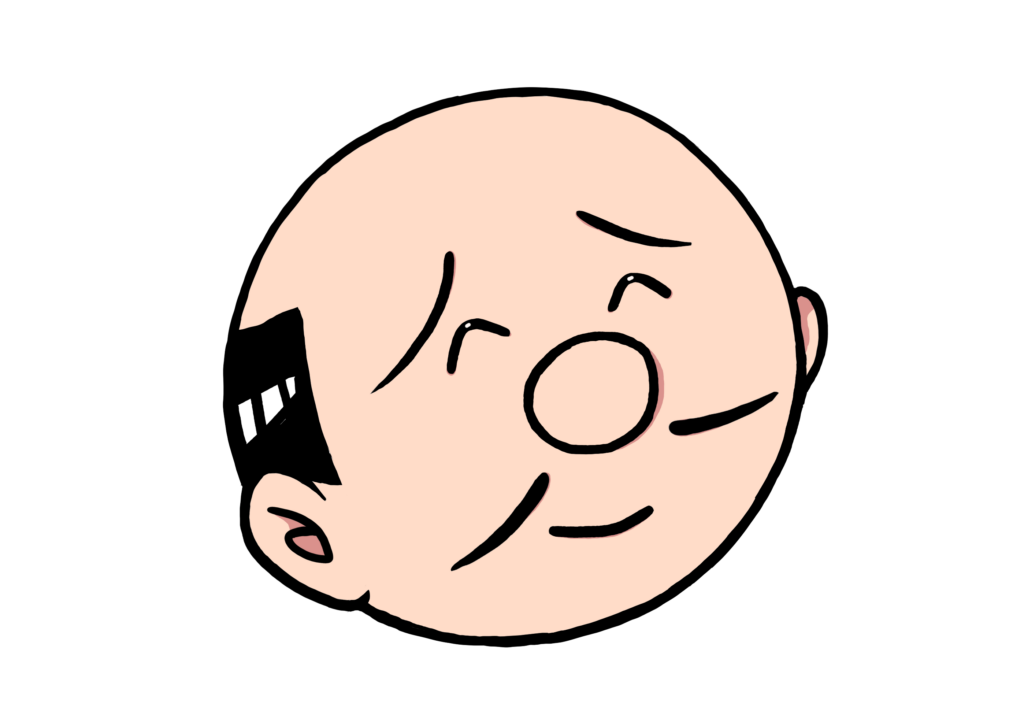
連結決算では、親会社と子会社の決算日がズレていることがあるよね。
この機会に、連結決算において、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の取扱いを整理しておきます。
原則
子会社が連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う(すなわち仮決算を行う)。
容認①
子会社の決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。
ただし、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な調整を行う。
【容認②】(連結財務諸表規則ガイドライン12-1)
【原則】の仮決算は、本来、連結決算日に行うべきだが、相当の理由がある場合には、連結決算日から3か月を超えない範囲の一定の日に仮決算を行うことができる。
(例)連結決算日が3月末の場合、8月決算の子会社の中間決算(2月末)を仮決算日として連結できる。
この場合、仮決算日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致についての調整を行うほか、仮決算日と連結決算日との間に生じた当該子会社と連結会社以外の会社との取引、債権、債務等に係る重要な変動の調整も行う。
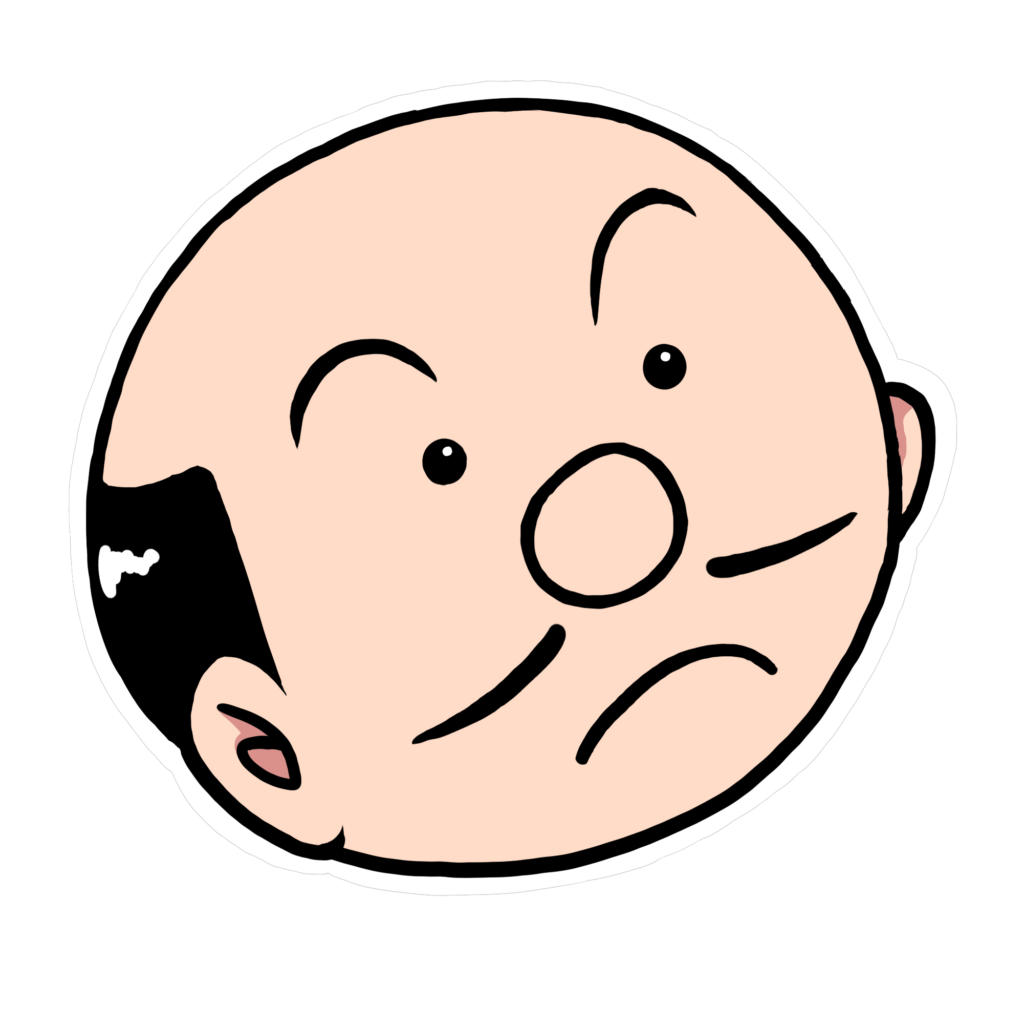
【容認②】の場合は、連結会社間の重要な取引の不一致だけでなく、仮決算日から連結決算日までに生じた連結会社以外の会社との重要な取引、債権、債務等の変動も調整することに注意!!
期間の『ズレ』をどう扱うか
温室効果ガス排出量は、そもそも見積りにより算定されるものです。そのため、算定期間と報告期間を合わせるためのコストは限定的と捉えることもできます。それよりも、両者の期間が大きくズレることによって情報の有用性が低下することのデメリットが問題視されたと言えそうです。
これに対し、連結決算に際して必ず子会社の仮決算を求めると、多大なコストが見込まれます。一方で、決算日がズレている状態で連結しても、短期間のズレのみを許容し、かつ、重要な点について調整を求めるなら、連結財務諸表全体としての情報の有用性が著しく損なわれることはないという考え方が採られていると解されます。
なお、容認規定に基づき、連結決算日と子会社の決算日がズレた状態で連結財務諸表に取り込んでいる場合、子会社に係るサステナビリティ関連財務情報も子会社の報告期間と同じ期間を対象として取り込むことになります。
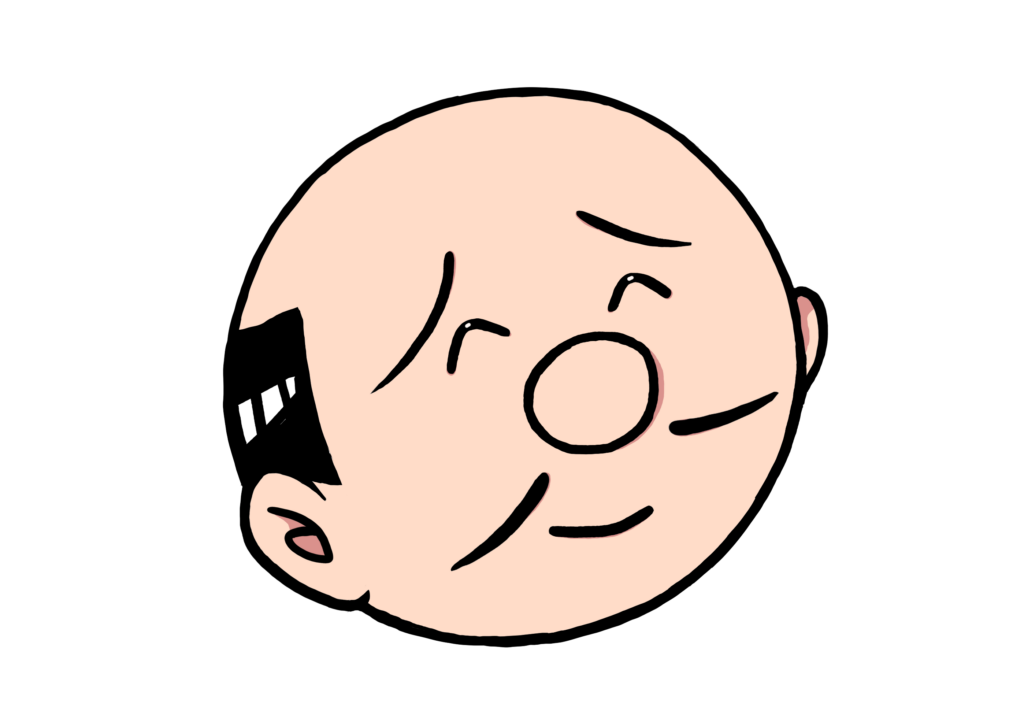
連結決算日が3月末で、12月決算の子会社について仮決算せずに取り込んでいるなら、その子会社に係るサステナビリティ関連財務情報も1月~12月分ってことだね。
ややこしいな~。


